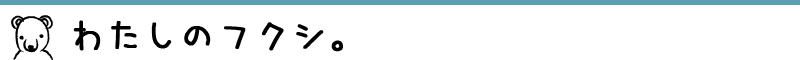シリーズ: シネマとフクシ(2)
「わたしを離さないで」
監督:マーク・ロマネク
原作:カズオ・イシグロ
カズオ・イシグロは、1982年にイギリスに帰化した、国籍上はイギリス人の作家である。長崎生まれで見た目は明らかに「ジャパニーズっぽい」が、行使するのは話し言葉も書き言葉もパーフェクトな英語であり、彼自身のアイデンティティも英語圏の作家だ。
カズオ・イシグロの小説は、読んでいるとクイーンズ・イングリッシュの朗読が耳元に聞こえてくるよう、詩的で情緒的。ひとたびページをめくれば、イギリスの郊外の古典的な田園風景が、行ったこともないのに頭の中で360度展開する。
2008年に出版された「わたしを離さないで」(原題:Never Let Me Go)。この小説が映画化されたと聞いたとき、「一体、どうやってこの本を映像化できるのだろうか」と、内心心配だった。わたしは個人的に、「わたしを離さないで」は、2000年以降に世界中で書かれた小説の中で、最も重要な作品の一つであると思っている。
「ヘールシャルム」と呼ばれる、森の中の美しい<施設>。イギリスの上流階級の子息が入学するバプリック・スクールのような寄宿舎、かわいらしい子どもたち。
キャシー、トミー、ルースの3人の描写が見事で、まるで自分の子ども時代を思い出す。そう、わたしもこんなふうにして、誰かに意地悪をしたり、後悔をしたりした。
観客は、この映画はハリーポッターの世界観のような「学園」が展開されるのかと一瞬思うが、画面の中に次第に「違和感」を感じ、落ち着かないざわざわとした感覚におそわれる。
古い城のような外観の<施設>に似合わず、奇妙なまでに精密すぎる健康診断。先生たちは「ティーチャー」ではなく「ガーディアン(保護官)」と呼ばれる。腕に埋め込まれているICチップ。そしてこの施設には、明瞭な<外>がある。境界線から<外>には、生徒たちは出られないのだ。絶対に。
<外>に出られない生徒たちのために、<外>の予行演習のようなものが行われる。施設内通貨で、<外>から運ばれてくるガラクタの様な、しかし生徒たちにとってはブリリアントなおもちゃを購入する。疑似的なカフェを舞台に作り、そこでメニューの頼みかたを学ぶ。
このシーンを見ていて、1960年~70年年代に、日本の重度心身障害児収容施設に入所していたある人のインタビューの一言を思い出した。
「「買い物の日」がありました。みんなで、施設で何十円かお金をもらって、施設の中のプレイルームでスナック菓子を買う訳です。」
これは、映画の中ではなく、現実にあったことについての話だ。
ふたたび、映画の世界に戻る。
「言うのが怖いの?」
そう、言うのが怖い。
「わたしたちの「オリジナル」は、クズよ。」
そう、ここにはもうこれ以上、詳しくは書けないけれど、きっとそうだと思っていた。
移植医療や再生医療、高度先端医療は、人間の社会にとって「過渡期の技術」であり、それで誰かが悪夢をみるも専門知のひとつとして役に立てるもまた、人間の社会しだいなのだと思う。
「でもね、キャシー、歴史的に見るとどうなります?
戦後、50年代初期に次から次へ科学上の大きな発見がありました。あまりに速すぎて、その意味するところを考える暇も、当然の疑問を発する余裕もなかったのですよ。突然、目の前にさまざまな可能性が出現し、それまで不治とされていた病にも治癒の希望が出てきました。」
「世界中の目がその点だけに集中し、誰もが欲しいと思ったのですね。でも、そういう治療に使われる臓器はどこから?」
「真空に育ち、無から生まれる……と人びとは信じた、というか、まあ、信じたがったわけです。ええ、議論はありましたよ。」
「でも、世間があなた方生徒たちのことを気にかけはじめ、どう育てられているのか、そもそもこの世に生み出されるべきだったのかどうかを考えるようになったときは、もう遅すぎました。」
「わたしを離さないで」 (p.401)
著:カズオ・イシグロ 訳:土屋政雄 2008年 ハヤカワepi文庫