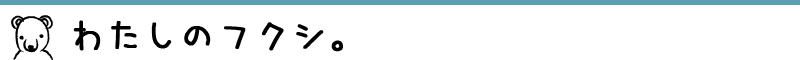ベッドに横になりながら、天井近くに設置したディスプレーを見つめる。Cさんは、唯一自分の意思で動かせる左手親指で、マウスを操作した。指定されたデザインの通り、名刺を作り上げると、笑顔になる。「どう、上手いもんでしょう」
筋ジストロフィーや筋萎縮性側索硬化症(ALS)など、重い神経難病患者が入院する石川県内の病院。患者の多くが、隣接する養護学校を卒業し、病院で長期療養に入る。一度も退院することなく、院内で一生を終える人も少なくない。
そんな患者たちに働く機会を提供しようとする取り組みが、2008年から始まっていた。同病院のソーシャルワーカー・Dさんが地元のパソコン教室と協力し、事業グループを結成。ブログ更新作業、名刺作りやデータ入力を請け負っていた。
私が病院を訪れたのは、富山県で働いていた2009年だった。筋ジストロフィーの後輩を失い、神経難病について真剣に取材を始めたころ、患者からこの活動を紹介された。「病院内で仕事をする」という、これまで聴いたことのない活動に、関心を持った。Dさんたちはなぜ、そのような取り組みを始めたのか。重い病気を持ちながらなぜ、働こうとするのか。見てみたかった。
当時、約10人の難病患者が参加していた。Cさんはその一人だった。筋ジストロフィーで、長く寝たきり生活。仕事に就いたことは一度もないが、パソコンは普段から使っていた。その特技を生かし、名刺作りやデータ打ち込みを担当した。作業効率は決して高くないが、指示通り的確に、作り上げていた。
一般就労を目指す車椅子の男性もいた。小学1年生のころから筋ジストロフィーで入院していたが、活動をきっかけに、集団面接会にも参加するようになった。移動介助や職場での援助を確保できず、実現はしていないが、今でも諦めず面接に向かっているという。
「地域に障害者の働く場を」。障害者自立支援法施行で、そんな声が広がりはしたが、病院内から出られない彼らに就労機会はない。「蚊帳の外」だった。「働きたい」、「社会にかかわりたい」。そんな思いに、Dさんらが応えた。「少しでも『働く』ことに近づける活動をしよう」
1人1人のニーズに合わせ、かなえる。そのために必要とする支援者の負担は、軽くない。パソコン作業にも資料を読み上げるボランティアが必要だし、移動には介助が不可欠だ。「面倒なことも多いよ。時間も人手もかかるからね」。Dさんは打ち明ける。
それでも続けるのは、仕事を得た患者たちが、充実した表情を見せてくれるからだ。何をするにも受け身になりがちだった態度も、積極的になった。生き生きとしていた。「本人が続けたいという気持ちを持っている。辞めたいというまで、私たちは付き合いたいのよ」
活動に関心を持つ患者だけを支援をすることに「公平性がない。特別扱いはおかしい」という批判を受けたこともある。
Dさんは首をかしげ、言う。「1人は良くても、他の人ができないから、で止めちゃう。でもそれっておかしくない? 1人1人違うし、求めているものも違うんだから。そもそも1人にできないことが、どうして他の人にできるというの?って私は思うの」
実行したのは、単純なことだった。それぞれの要望を聞き、かなえるために必要な力を集める。ただそれだけ。Dさんたちは、1人1人に公平に接することを心がけていた。
Cさんが人生で初めて手に入れた報酬は、百円玉1枚だった。その額に少し戸惑ってしまった。私の表情を察したかのように、Cさんは笑った。「嬉しかったよ。初めて自分の力で手に入れた給料だから。まあ、すぐに使っちゃったけど。でもね、あの1枚の重みは、忘れないよ」