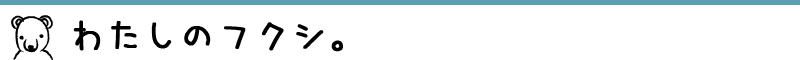一通り話を聞き終え、ノートを閉じる。正面に座る取材相手がふと、こちらを向いて尋ねる。「勉強していたわけでも、ボランティアをしていたわけでもないのに、なぜ福祉の取材をしようと思ったのですか」。結構頻繁に、こんな「逆質問」を受けていた。
あれ。そういえば、なんでだろう。
2005年の入社以来、全国を転々とし、担当もスポーツ、警察、行政と毎年のように替わった。そんな中、一環して続けてきたのが、福祉関係の取材だった。
きっかけ自体は、行政の発表文だったり、気の置けない友人が増えたりしたことだろう。でも、そもそもなぜ、興味を持つようになったのか。当初はこの質問にしばらく、答えが出せなかった。「力になりたくて」みたいな言葉で、ごまかしていたように、思う。
入社して3年が経ったころだった。大学時代の後輩から「A君が危篤です」という連絡があった。
A君は、大学時代に所属していたサークルの後輩。私にとって、障害を持つ初めての友人だった。進行性の難病「筋ジストロフィー」の患者で、出会った時はすでに車いす生活。ほぼ全身が動かなかった。トイレの介助も必要で、いつも母親と一緒だった。
進行性の病気で、いつ悪化するか、命を失うか分からない。でも部室に来る彼は、そんな「恐怖感」を感じさせなかった。活動にも飲み会にも積極的だったし、勉強を重ねて大学院にも進学した。わずかに動く手を使って、ゆっくりとパソコンのキーボードをたたく姿が、今も鮮明に残っている。
出会って最初のころ、私は少し戸惑いを持ちながら接していた。十分な配慮ができているのか、気を遣い過ぎて窮屈にさせていないか。その境界線が分からなかったからだ。
一方、一緒に過ごす中で、見逃していたことに気づくようになった。歩道にある数㌢の段差や、自転車が行き交う道の恐怖感。合宿用の宿泊先を探そうとしても、スロープ付きの玄関やエレベーターを備えた施設が少ないこと。彼との付き合いが、日常にある「不自由さ」を知るきっかけになった。
卒業後に再会したのは、告別式だった。その席で、親の反対を押し切り、病気の研究のため、自身の遺体を解剖に提供する「献体」を申し出ていたことを知った。体が震えた。難病と向き合い、その選択をした彼を心から尊敬し、そして後悔した。もっと、話を聞きたかった、聞いておくべきだった、と。
当事者でもなければ、障害のある家族がいるわけでもない。そんな私が「伝え手」になるのは、いつもどこかで「おこがましいなあ」と思っている。
でも、当事者の声を伝える「手段」だけは、持っている。もしかしたら、自分一人で苦しみ、声を上げることができずにいる人に、仲間がいるんだよ、ということを届けることができるかもしれない。理解することはできなくても、「理解したい」という気持ちを広げることができるかもしれない。私が彼と出会った時のような「気付き」のきっかけになるのかもしれない――。
彼と知り合い、この仕事に就いたのは、偶然ではないと思っている。
今、冒頭の質問があった時、私はこう答えるようにしている。
「友人との出会いが、原点です」
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
「新聞記事」を書く時、取材した内容が10あるとすると、その中から採用できるのは1、2もないくらい。いろんな制限・制約もあるし、伝えきれないこともたくさんある。この場では、普段の記事には書ききることができなかった、「ノートの端っこ」にある物語や、私の思いを、綴りたいと思います。