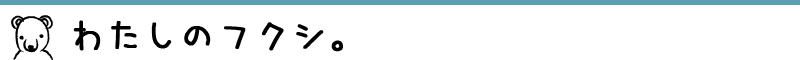茨城県南部の住宅街。路地を抜けていくと、10年以上前に見た景色をおぼろげに思い出す。A君の父親の運転する車を降りると、A君の母親が玄関から歩いてきた。「蒔田くん、久しぶりだね」。明るく、柔らかい声で出迎えてくれた。
この春、九州・佐賀県から茨城県に転勤した。10年前、大学時代を過ごした場所。2月に佐賀で内示を受けた時、すぐ頭に浮かんだのは、A君の顔だった。
A君のことは、「ノートの端っこ」の第1回 「逆質問」で書いた。大学時代のサークルで一緒に活動し、6年前、持病が悪化して亡くなった。
告別式に参列して以来、茨城に来ることも、両親に会うこともなかった。会おうと思えば、できなくはなかった。なぜなのかは分からないけれど、積極的に会おうという気持ちを抱くことができないでいた。転勤という、半ば「強制的な移動」という条件を得たことが、きっかけになった。
自宅に上がり、初めて仏壇と向き合った。数分間、目を閉じた。「もっと話をしたかった、いま、話したかったよ」。そう、つぶやいた。
仏壇の脇に、1冊の本が置いてあった。
A君の死後、教員や同期生らが作成した追悼文集だ。A君に宛てて友人らが寄せた文章と、A君が大学時代に執筆した文章、論文を掲載している。私も寄稿した。
就職後、私は何度も読み返した。A君のことを何度か記事にしたという面もあるけれど、難病や障害のことを、何も知らなかった当時を思い返す作業でもあった。
「まだ、ちゃんと読めていないのよ」。その文集を、両親は今も、すべてを通して読むことができていない、という。
訪問することに合わせて、私の文章に目を通してくれたそうだが、父親は「やっぱり……ダメですよね」と声を詰まらせた。母親も「どうしても、泣いちゃって」と、笑顔のまま、涙を流した。
その瞬間、なぜ今まで、この家に来ることができなかったのかということが分かった気がした。
2人は、A君を失ったという事実を亡くなったその日から途切れず、目の前に見ながら生きている。一方で私は、A君のことを「過去の話」にしている。そのことがはっきりした。「愛する子どもなのだから」「家族と友人は違うから」……。そうかもしれない。でも私は、「みんなと同じように、私もA君の死を悲しんでいる」「一定の時間がたったから、気丈な両親はきっと、気持ちの整理をある程度つけているだろう」というストーリーを頭に描き、当てはめてしまっていたのだと思う。それぞれの受け止めも、悲しみも、全然違うのに。
両親の愛情と悲しみに、現在進行形であることに、十分目を向けることができていなかった。自分の感情ばかり優先させていた。その整理をつけることができていなかったから、距離を置いてしまっていたのではないかと感じたのだ。
来て良かった、と思った。今もA君が目の前にいるかのように、愛し続ける2人を知ることができた。2人のようにではなく自分は自分なりに、A君のことを忘れず、思い続けよう、と改めて考えることもできた。
父親は会社を退職後、障害者施設で働き、母親も病院で勤務する。A君の友人は今も、自宅を訪ね、両親と食事し、酒を飲み交わすという。母親は、言う。「Aはいなくなっちゃったけど、どこかでつながっていて、みんなの中にいるんだって。友だちも、忘れずにいてくれるんだなって。それがすごくうれしいの」
3人でビールを飲み、A君の母親の手料理を味わい、当時は聞くことのできなかったA君の話を聞いた。「いつでも来ていいからね」。2人の言葉に「必ず、また来ます」と返した。