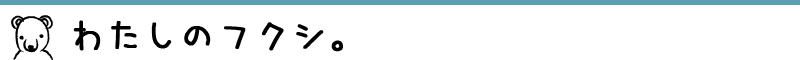佐賀県内の高齢者施設の一室に、白衣にサングラスをかけた男性、Eさんが入る。隣に歩く私の肘をつかみ、一歩一歩、その先を確かめながら足を進める。その目には映らないが、ベッドに座る高齢男性に確実に向かい、声をかけた。
「こんにちは、おじいちゃん。体調どうね。変わりなか?」
男性はEさんの姿を見て、顔全体をくしゃっとさせる。「はい、はい、元気ですよ。いつもありがとねえ」。Eさんは横になった男性の体にタオルをかけ、ゆっくりと体をもみ始める。背中、首、肩、足首。声をかけて確認しながら、マッサージする。
「痛くなか?」「ここは大丈夫?」。声をかけることを忘れない。「話し相手」になることを心がける。顧客それぞれの特徴、症状を思い出しながら、体に触れていく。
Eさんは今年4月、マッサージ師として働き始めた。「網膜色素変性症」という難病で5年程から視力が一気に低下した。それと同時に、手にしていた「幸せ」が、崩れていった。
約15年前、建設会社を立ちあげた。主に公共工事を手がけ、多いときには同時に4つの現場を抱えていた。「仕事をすればするだけ、金が入ってくる。全てがうまく行っている」。疑いなく、そう思っていた。
兆しは、あった。工事の設計図が二重に見えるようになった。眼科に通いもしたが、意に介さなかった。
不和で妻と離婚協議を始めたころから、「順調な生活」は揺らいできたように思う。妻は3人の子どもを連れて家を出た。ストレスで体調を崩したこともあってか、視力は急落した。
仕事に影響も出始めた。視界は常に曇って見え、平らな道で転ぶようになる。発注を受けた部屋の色と別の色で仕上げてしまうこともあった。運転もできなくなり、現場に行けない。負債が積み上がり、自己破産した。
家族が去った、約60坪の2階建て住宅。「お帰り!」。迎えてくれた子どもの声がない。部屋のドアを一つずつ明けても、空っぽだった。一人で過ごすには、あまりに広すぎた。1日中誰とも会わない「引きこもり」生活になった。
その「喪失」から5年余り。笑顔で仕事をするEさんの姿が少し、信じがたかった。決して長くないその時間で、どうして、受け止めることができたのか。前を向くことができたのか。私は正直、理解できなかった。
ストレートに質問すると、少し苦笑しながら、答えてくれた。「いや、今でも引きずってますよ」。少し間を空けて、「でもね、支えてくれる人に出会ったから、このまま一人で沈んでいてもダメ、という気持ちになれたのだと思うんよ」。
患者を支える「難病相談・支援センター」のスタッフや、盲学校の教師は、他人のEさんに、自分のことのように親身に応援してくれた。最初は、彼らのことを「仕事、利益ばかり考えていた自分や、周りにいた人間とは違う人種なんだ」と感じていたが、「違う」と気付いた。「病気になって、目が見えなくなって、自分が変わった。人の思いやりを感じることができるようになったんだって」
社長をしていた時より収入は減り、帰宅すれば、1ルームの部屋にひとり。それでも、今の生活は充実している、と言える。高齢者、自分と同じように治らない病を抱える難病患者。その一人一人と向き合い、マッサージをして、笑顔にすることができる。仕事をした分、感謝してもらえる。何にも代え難い、生き甲斐だ。
「今でも、視力が戻ったら、って思いますよ。綺麗な女性の姿も見たいしねえ」。笑って、続ける。「でもね、違うんだな、って。人にはそれぞれ、生きるべきレールが敷かれている。私は今、本当のレールに乗っていると思うのです」
悔しさも、心残りも胸に抱えた上で、そうはっきり言葉に出せるEさんが、まぶしかった。