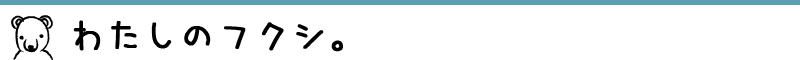箱に大事に閉まってある写真が外に出され、目の前に置かれたとき、一瞬、つばを飲み込んだ。写真を撮るつもりで「見せてください」とお願いしたものの、いざとなると直視することにためらいが出てしまった。
その中心に映っている新生児、Oちゃんは「生きてない」。その子を抱く母親Pさん、囲む夫の男性、長女、長男。全員が笑顔だった。セルフタイマーで撮影したその写真は、不自然さが一切なかった。こういう1枚を幸せな家族写真そのもの、というのかなとも感じた。「この時が、一番、幸せだったんです。ああ、本当に幸せだったなあ」。Pさんは、その時を思い出し、慈しむかのように、声を漏らした。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
妊娠8カ月のころ、胎児の心臓に穴が開いていることが判明した。詳しい検査で染色体異常症「18トリソミー」であることが分かった。無事に産まれる可能性自体が低いこと、対面できても生存確率がきわめて低いことを告げられた。
「何もできないんですか、私」。医師は首を振った。「手術すればいいんだろう」と思っていた。自分のお腹の中にいるのに、病気があるのに、何もできないでいることがもどかしくて、悲しくて、つらかった。
中絶する時期は過ぎており、「今後、どう対応するのか」という選択を迫られていた。「できる限り自然な形で産みたい」という思いから、自然分娩を選んだ。いつどうなるか分からない状況だったが、「流産していたかもしれない命。ここまでがんばってくれたのだから、できる限りのことをしよう」と考えた。産まれたとしても、どこまで手を施すべきなのかすべきでないのか、答えは出ないままだった。「産まれないと分からない」。そこまでしか考えられなかった。
病気については、あまり調べなかった。「前例」を知ると、それを目標にしてしまう気がしたからだ。1歳まで生きられるのが1割未満という病気だから「なぜ自分の子は生きられなかったのか」という気持ちに囚われてしまうのが嫌だった。
怖さよりも、会える楽しさが勝っていた。「いつ、命が終わってしまうかも分からないけど、今、一緒に過ごせる時間を大切にしよう。きょうだいの声をたくさん、聞かせてあげよう」。そう考え、家族で動物園に行ったりもした。生活は、過去2回の妊娠と、何ら変わりはなかった。
予定日の朝、病院に入り、出産を間近に控え、陣痛室に入った。胎動が弱くなっていた。詳しく調べたところ、亡くなったことが判明した。
何日でも、何時間でも良いから、産まれて対面したかった。「親のエゴかもしれないけど……」。死産は、戸籍に入らない。生きた証を、名前を、残したかった。
「後は自分の思う時でいいですよ」。病院側からそう告げられ、夫と陣痛室で2人で話をした。「なんで今なんだろう。抱いてあげられると思ったのに」。Pさんが言うと、夫は「お腹の中から離れたくなかったんだよ」と答えた。しばらく過ごし、「早く抱いてあげよう」と部屋を出た。
分娩は、約1時間だった。Pさんは、「ずっとお腹の中においておきたい」「早く抱きたい」という正反対の気持ちが混在していた。産まれたとき、泣き声は聞こえなかった。体はチアノーゼで紫色だった。抱いた瞬間、「ああ、うれしい。やっと会えたね」と思った。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
私が写真を見ることに一瞬おののいたのは、事実として「死体を写す」という恐怖感があったこと、また、死産が「不幸せ」というイメージをぬぐえなかったからだ。
「病気があるというだけで、不幸でもかわいそうになるわけでもない。18トリソミーでなければ良かったとは思っていない。この病気があるから、Oだったと思っています。」。取材時、Pさんはそう、はっきりと口にした。
元気で生きて産まれることを、きっとみなが望んでいただろう。取材していた部屋には、きょうだい2人が、おもちゃを広げて遊んでいた。その輪に、Oちゃんがいたら、と私ですら想像してしまっていた。
それでも、こうした言葉に出せることが、Pさんの言う「幸せ」を体現している、とも感じた。そしてそれを疑えないほど、写真のPさんは、柔らかく、暖かい表情をしていた。これほどの笑顔は、今まで見たことない、と思ってしまうほど魅力的だった。
長女は、「ほんとうのOちゃんはいつ来るの?」という問いを投げかけたことがある。きょうだいが、妹の命をどう受け止めているかは、まだ分からない。いずれ分かってくれる時が来ればいい、とPさんは思っている。焦ってはいない。
家族として過ごすことができたのは、火葬までの4日間。「あのときがなければ、こうして笑顔で過ごすことはできなかっただろうなあ」と、思っている。
Pさんは今、同じ患者の子どもたちのありのままを伝える写真展の活動にも取り組んでいる。子どもを「18っこ」と呼び、家族の声を届けている。
どれだけ前向きにとらえても、「目の前にいない」という悲しみは消せない。同じ病気の子どもがいる家族同士だからこそ、そういう感情を、安心して話すことができた。「私にも居場所がある」と思えた。自分や家族がいなくなったら、だれもOちゃんの存在を知らない。「Oのことをみんなに知ってほしい」という思いもあった。
佐賀で開かれた写真展を、私も訪ねた。すでに亡くなっている子も多く、生きている子も呼吸器を着けたり、何度も手術を受けていたり、全介助が必要だったりするようだった。暮らしぶりの困難さが頭に浮かぶと同時に、家族が切り取っただろうその表情に、見入ってしまった。
Pさんは「この写真を見た人が、重篤な病気イコール不幸、という方程式をなくしてくれたらいいな、と思うんです」と言う。その方程式は、完全にとは言えないけれど、私の中でもう変化しつつある。