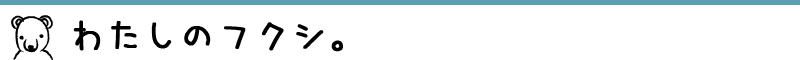バッグの中から折り紙を取り出すと、Mさんは「CMを見て覚えた」という「メガネ」を折り始めた。Mさんの手の中で動く折り紙は、踊っているかのように映るほど優雅に姿を変え、数分で完成した。その作品を、そっと両手で包み込むようにして、カメラを構えた私に向け、掲げてくれた。
小学生の時、「てんかん」を発症した。突然意識を失うなど強い発作があり、高校生の時、治療のために脳の手術を受けた。そのころから、人の名前を覚えにくくなったり、熟語の意味が分からないようになった。メールやメモの文章を見て覚えることは比較的得意だが、聞き言葉、会話を頭に入れるのが困難だった。
学校側の協力もあり、短大に進学した。保育士を目指していた。しかし、勉強についていけなくなった。人の名前やスケジュールが覚えられず、団体行動に強いストレスを味わった。友人、家庭の人間関係に苦しみ、自傷行為を繰り返した。後に、「高次脳機能障害」と診断された。
学校も退学し、居場所を失っていた中で、心の拠り所になっていたのが、折り紙だった。
入退院を繰り返していた幼い頃、病院ボランティアの女性から教わった。「正方形1枚の紙から人形、風景、さまざまな形が生み出せる」。その魅力にとりつかれ、時間が空けば、作っていた。今も、外出するときにはバッグの中に常に、折り紙を入れている。
折り方も自然と覚えることができた。教本、見本を見て、何度も練習し自分のものにする。指導者としての「資格」も取得し、子供たちへの折り紙教室も定期的に開催するようになった。作った作品は100点以上。「私でも、教えることができるんだ。覚えることは苦手でも、こうして力になることができるんだ」。自信になった。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
私が初めて会ったのは、2年程前。折り紙作品の展示会だった。Mさんは外見からは、障害があるかどうか分からない。身体的な支援が必要な状態ではなかったし、私の前で不安定な表情を見せたこともなかったことから、メールをしたり、対面して話をしたりしても、「同年代の女性」という意識しか持たずに付き合っていた。あらかじめ聞いてなければ、「障害者」とは分からなかったと思う。
一方で、Mさんと向き合うとき、「障害者」と認識している自分が、どういう態度で話をしているのか、どういう視線を向けているのか、不安になった。同年代ということで、より身近に考えたこともあるかもしれない。
「疲れてないですか」「この点、もう少し聞いてもいいですか」――。そんな言葉を出すたび、障害があることを過度に意識した態度になっていないのか。極端に言えば「差別意識」を働かせていないか。笑い話をしながらも、自分に「疑問」を投げかけていた。Mさんが抱える見えない障害に、自分の中にある見えない意識に、思いを巡らせていた。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
6月上旬、Mさんは、同じ障害のある陶芸家の男性とともに、展示会を開いた。訪れた私に、「最近作った」という作品を見せてくれた。佐賀県内に流れる川と、その岸に漂うこいのぼりと、満開の桜が並んでいた。入院中だった病院から外出許可を得て花見をした時の風景を再現したという。
「入院中で花見ができない仲間に、桜を見せてあげたかったんです」。そういって、Mさんは笑った。額に入ったその作品を取り囲む、患者さんたちの笑顔が目に浮かび、思わず「素晴らしい」と声を上げてしまった。
彼女が障害から由来して感じている苦しみや、悩みについて、私は十分、聞き取れても受け止めもできていない。今いっときのMさんの姿を見て、「障害なんて関係ない」なんて、軽々に言うこともできない。それだけ理解できているとも思えない。実際、6月の展示会中もMさんは入院中だった。外出許可を得ながら、生活をする準備をする段階で、不安定な状態は今も続いている。そういう状況も私は十分、把握できてもいない。
どう向き合えているのか、今も分かっていない。
ただ言えるのは、不器用な自分には到底できない技術を身につけていること、それによって多くの人の笑顔をうみだせること。その深い思いやりを持つMさんに、心から敬意を抱いている、ということくらいだ。