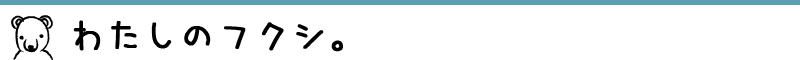看護師のIさんは北海道函館市から医療ボランティアとして、被災地に入った。岩手県沿岸部を中心に避難所や被災者宅を訪問し、心と体のケアに当たっていた。
特別な思いがあった。
Iさんは1993年に発生した北海道南西沖地震による津波で、両親と実家を失った。2人の遺体が発見された翌日、現地に向かった。母親の体には、砂が入り込んだ。いくら拭き取ってもぬぐえなかった。
火葬後、函館に戻る船の中で、受け止められず呆然とするIさんを、付き添いの同僚看護師が抱きしめた。初めて、涙が出た。体の中に重く沈んでいた悲しみを、一緒に引き上げてもらえたような感覚だった。少しだけ、心が軽くなったような気がした。
2年後、阪神大震災が起こった。ボランティアの要請は来たが、受けることができなかった。両親の死が、悲しみがよみがえってしまうことが怖かった。「行きたい、でも行けない」。複雑な気持ちを抱えたまま、現地に向かう同僚を見送った。
だからこそ、今回の派遣に込めた決意は固かった。街が津波にのみ込まれる様子をテレビで見た時、「私が行かなければいけない」と確信した。「津波で親を失った私だからこそ、悲しみを分かち合うことができるかもしれない」と思った。
2つの震災を経験したHさんを、Iさんは特に気遣った。避難所を訪れるたび声をかけ、マッサージをした。肩を、足を、もみほぐしながら「大変だったね、悲しかったね」と語りかけた。時に、肩を抱いた。「私もね、津波でお父さんとお母さんいなくなっちゃったんだ」。励ましたり、鼓舞するような言葉は私が聞いていた限り、一度も使わなかった。
近くでじっと聞くことはできなかったけれど、Hさんは一言二言、と言葉を漏らした。Iさんは、ただ頷いていた。約15分のマッサージが終わると、Hさんの表情は少し、和らでいるように映った。
訪問2日目。IさんはHさんから、手紙を受け取った。感情が詰まったその文章を読み、Iさんは少し安心した。「感情を、悲しみを、はき出すことができたなら、きっと大丈夫。少しずつでも、大丈夫」。自分自身もそうだったから、分かる。
3日目、Hさんは避難所に入って以降初めて、街を歩いた。建物だった残骸が広がり、道路がゆがみ、車や船が崖上に乗り上がっていた。パートナーと手をつなぎ、「カフェ」にも帰った。土台しか残っていなかった。
私は避難所に戻った直後のHさんと対面した。Hさんは笑顔を向け、語った。「何も、無かったよ。でもね、仕方ないものね。失った物は戻らないからね。これから生きていかないといけないからね」。無理をしているのは分かったし、どんな言葉も見つからなくて、私はただ、頷いた。
HさんはIさんにも報告した。「そっか、よく行ったね」。その一言で労い、後は食事のことなどで楽しげに雑談を続けていた。
前を向こうとするHさん。その背中を、Iさんはそっと支えた。悲しみを抱えた邂逅だった。つないだのは、地震、津波。喪失が生んでしまった出会いだった。けれど2人が向き合い思いを分かち合ったことに、笑顔で会話を交わす姿に、光を、何らかの「希望」を見出していた。
「新しい場所で、新しい家を建てる」と言っていたHさんは、どうしてるだろう。函館に戻ったIさんは、被災地にどのような思いを寄せているだろう――。17年目の1月17日を過ぎ、3月11日が近づいている。