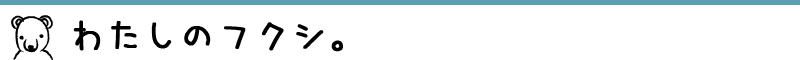高台にある公民館に入る。建物奥の畳部屋はカーテンが閉まり、数十の布団が敷かれたまま。うす暗い。テレビの前に、ぼんやりと座る高齢者がいる。
4月、東日本大震災の被災地、岩手県大船渡市にある避難所を訪れた。取材した時点で、50人以上の被災者が寝泊まりしていた。数日通い、10人以上に話を聞いた。その中で特に、気になる人がいた。
その女性Hさんは当初訪れた時、ほとんど身動きしなかった。部屋の一番隅に座って毛布にくるまり、手に取った文庫本をぼんやり眺めていた。「彼女に話を聞くのは、ちょっと難しいよ」。気にする様子に気付いた別の被災者から、そう声をかけられた。
1995年1月、彼女は神戸市中央区で暮らしていた。その月の17日午前5時46分、大きな揺れが襲った。6000人以上の命を奪った阪神大震災。けがは無く家族も無事だったが、数カ月後、神戸を離れた。
北陸、大阪を転々と暮らした。途中、夫と別れ、子どもと離れて暮らした。一人で生活する忙しさに追われる中で、ある男性と出会った。「三陸海岸でカフェを開きたい」。パートナーの夢を一緒に追うため、2010年11月、大船渡市に移住した。
好きな場所で、好きなことを楽しみたい。それが願いだった。パートナーは陶芸を、Hさんは手織り品をそれぞれ並べた。「地域の憩いの場にしよう」と、訪れる人にとって居心地の良い空間にしようと心がけた。常連客が集まり始め、初めての春を迎えようとしていた時だった。その日が来た。
16年前よりも、激しい揺れだった。窓のすぐ外に広がっていたはずの海へ目を向けると、水が引き、海底がのぞいていた。知人から聞いていた光景だ。「津波が来る」。直感した。荷物をほとんど持たず、パートナーとともに高台へ避難した。
住んでいた場所を見た。サイコロのように家が流れていた。2人で作った食器、思い出、跡形もなかった。その光景が焼き付き、幾度無くまぶたの裏に浮かんだ。
避難所で過ごすようになり、Hさんはふさぎこんだ。2つの震災を経験した人は、周りにいない。阪神大震災を経験したことは、地域住民も知っていた。周囲の目が気になって仕方がなかった。
「震災を、津波を招いたのは、私のせいだ」。外から来た自分が、不幸を呼び込んだとしか思えない。息苦しくなり、でも、傷跡生々しい街中を歩きたくない。行き場をなくし、避難所でただ、呆然と過ごしていた。
「こんにちは。大変だったね」。
白衣姿の女性、IさんがHさんに声をかけたのは、そのころだった。